ENEOSグループが切り拓く未来:AI活用により業務変革や新しい価値の創造に挑む
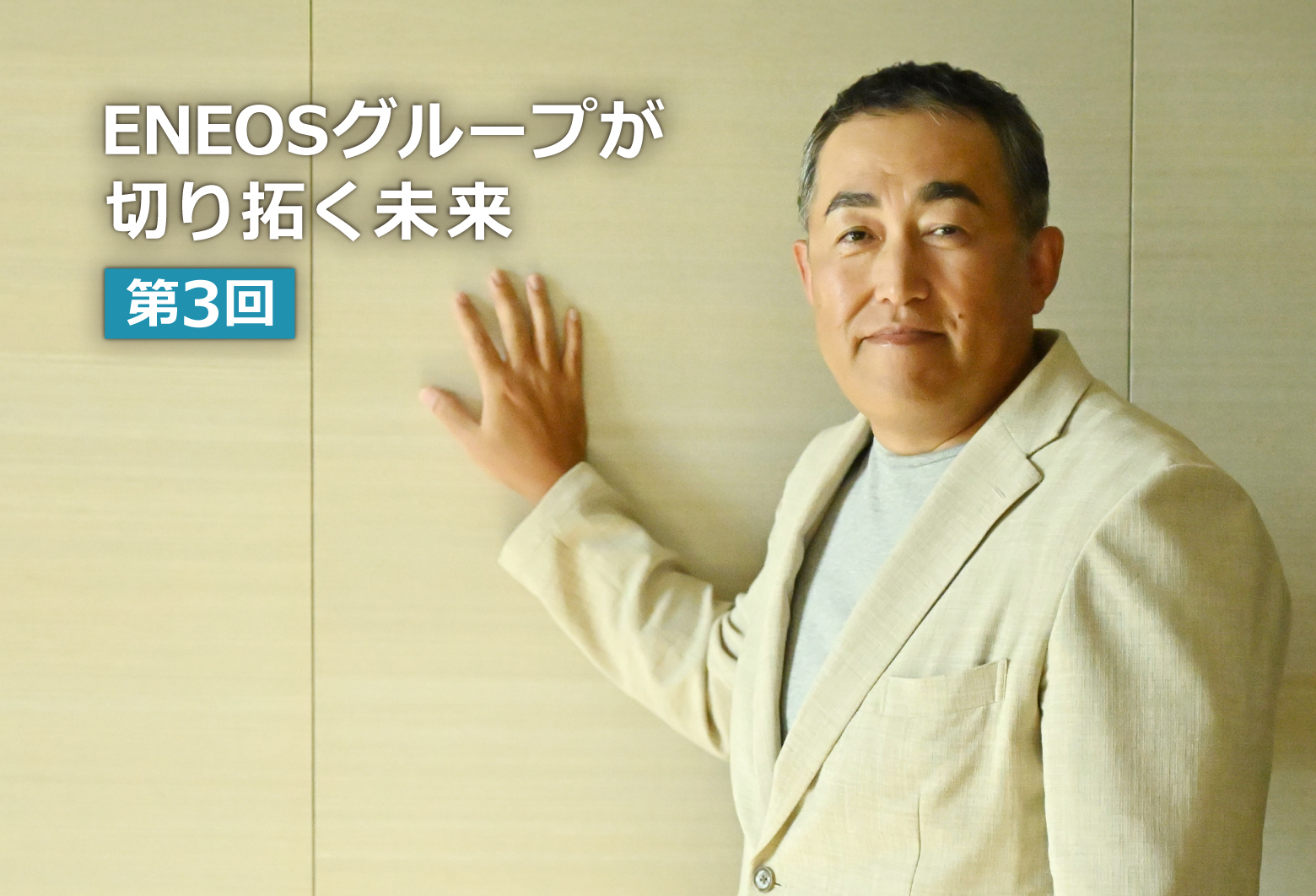
エネルギー業界のリーディングカンパニーENEOSは、2024年に川崎製油所での世界初の原油処理装置の自動運転を実現するなどAI活用においても業界を牽引する存在だ。ENEOSでは業務変革と価値創造を実現する「AIを活用した明日のあたり前」を目指し、①データ活用、②デジタル技術力、③デジタル・IT人材、④セキュリティという「4つの原動力」を強化している。本連載(全3回)ではENEOSのデジタル戦略の司令塔・IT戦略部の田中司部長に、AI活用の現在地と「明日のあたり前」について聞いた。
第3回:AIとともに進化を続ける
AIとビジネスが協調する未来へ
AI活用による“真の成果”を
全社員に受け取ってほしい
――今回は、ENEOSがAI活用によって目指す姿、「明日のあたり前」について伺っていきたいと思います。まずは、AIの活用でどんな業務改革を行っていきたいと考えていらっしゃいますか?
田中 日本では少子高齢化の進行で今後、労働力人口がますます減ってきますから、AIを活用することで業務の省力化やスピードアップを図ることが、まず1つ。加えて、原材料調達や物流など大きな資金が動く分野で、AIを使って効率化を進めていきたいですね。
――人的資本の有効活用、さらに収益力向上につなげていくわけですね。新しいデジタル戦略では「筋肉質な経営体質」への転換に向けてENEOSの供給・販売・製造領域での強化を挙げています。
田中 当社のデジタル化はこれまで、さまざまな部門、部署に向けた全方位的なものでした。しかし、ENEOSホールディングスの現在の経営計画(第4次中期経営計画)が掲げる「筋肉質な経営体質」を目指すには、収益がしっかりと出る部分から優先順位をつけて、取り組んでいく必要があります。ENEOSグループにはいろいろな事業会社がありますが、核となるENEOSの石油精製販売事業の根幹をなす供給・製造・販売を軸にAI活用を進めていく。そこでキャッシュを生み出して、さらに業務も効率化していく。そして、最終的には、全社員がAI活用の恩恵を受けるような取り組みにしていきたいと考えています。
――具体的には、どんな取り組みを行っていくのですか?
田中 IT部門だけで独りよがりなAI導入、AI活用をやっていくわけにはいきませんから、デジタル戦略の中でそれぞれの事業で本当に何が必要なのかを事業部門と話し合いながら、取捨選択していく必要があります。第1回(ENEOSグループが切り拓く未来:AI活用により業務変革や新しい価値の創造に挑む | ENEOSWAYS | ENEOSホールディングス)でお話しした横展開も重要です。ここの部門だけではそれほど価値がなくても隣の部と一緒に取り組んだら成果が出そうというものについては、私たちが積極的に橋渡しをしていくつもりです。
――そこに向けて、デジタル人材やデータ活用の仕組みなど、これまでに準備してきたリソースをどんどん投入していく感じですね?
田中 育成したデジタル人材がシステム化の案件にあまり関わっていないケースも散見され、人事とも相談しながら、ENEOS全体でのデジタル人材の最適な配置や活躍を仕掛けていきたいと考えています。データ活用については、当社は依然「Excel大好き」なので、データ活用を訴求するに当たっては「脱Excelをやると、こんなにいいことがあるんですよ」という具体的なイメージを示していきたいですね。CoMPASSのデータはもちろんですが、当社はCoMPASS以外にも製造系や物流系の膨大なデータを保有しており、そこを活用しない手はありません。そうした中から事業に貢献していければと思うのですが、デジタルの場合は貢献の因果関係を証明するのが難しい面があります。パソコンの動作が速くなりましたと言っても、労働密度が上がるだけで残業時間は減りませんからね。しかし、デジタルはツールで構わないので、あくまで事業として成果を出してほしいと思っています。
――そうした中で、「IT戦略部はAI活用の旗振り役として吸収していかなければならない知識が山ほどある」とおっしゃっていました。
田中 そうですね。ChatGPTなどの生成AIは出てきてまだ2年ほどですが、成長著しく、そこはしっかりキャッチアップしていく必要があると考えています。私がIT戦略部長に就任した時に、部員には「1週間の労働時間のうち1割くらいは技術習得に割いてほしい」と要望したのですが、今、IT戦略部は足元の業務にてんてこ舞いで、皆、ほとんど時間が取れていない。生成AIの研究ができるくらいの環境を用意してあげなければと思っています。

――田中部長ご自身は日常業務の中で生成AIをどれくらい活用されているのですか?
田中 私自身は生成AIのヘビーユーザーを自認しています。部下との議論は長引くこともありますから、あらかじめAIと想定問答を繰り返した後に話を始めるようにして効率化しています。最近のAIは1つの質問に対して幅広い角度から多様な答えを返してくれるので、そこからアイデアが広がることが少なくありません。新しいシステムの導入などに当たっては、それによって社内にどんな効果があるのか、経営陣を納得させるストーリーを構築する際の参考にしています。
――ご自身の経験を通じて、AIの浸透が社員にもたらすメリットはどのような点にあるとお考えですか?
田中 少々抽象的な話になりますが、たとえば、AとBの2つからどちらか一方を選ぶとします。直感でAを選んだ人が、その後Aの方が安価で質もよく環境に配慮した製品だと知ったら、「ほら、言った通りだろう」と気を良くするでしょう。しかし、実際にはその人が「直感」で選ぶ段階で既に、AとBの良し悪しについて、決断に足るだけの理解がなされているわけです。一方で業務ではこうしたときに理由が求められ、その収集・分析に時間を要するものです。AIの利用は、例えばこの根拠の収集に費やす時間を削減し、決断のような価値が大きいことに費やす時間を増やすことに貢献できます。常にデータに基づいた適切な根拠をくれる気持ち良さから社員はAIを使うようになるし、決断をするために必要な時間が減って会社的にもコストダウンにつながります。AI活用の真の成果はたとえばこうしたところにあるのです。
――なるほど、AI活用のイメージが湧いてきました。最後に、「AIを活用した明日のあたり前」に向けて、IT戦略部としてどんな役割を果たしていきたいかをお聞かせください。
田中 一言で言うなら、「高度にいいあんばいにしたい」という気持ちです。第1回でもお話ししたように、湯水のように資金を使っていいのであれば、いくらでも使える世界です。しかし、デジタルにばかり投資するわけにはいかないので、費用対効果というところも見ながら、良いものをしっかり選んでいくのが私たちの仕事と考えています。AIを活用した先に新しい時代が広がり、そこではAIとビジネスの協調が「あたり前」になっているのではないかと思います。そうした「明日のあたり前」がスムーズに提供できるように、今できることはできる限り戦略的にやっていきたい。それが実現して当社が発展し、より良く社会やお客様に貢献できるという状況になっていくのだとすれば、IT戦略部の業務は本当にやりがいのある仕事だと思います。






